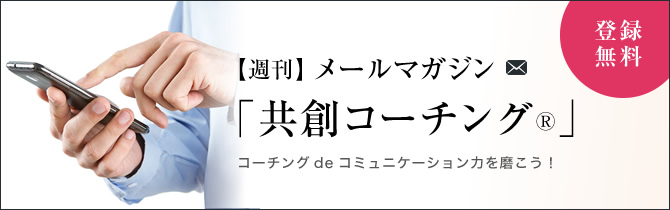おはようございます。共創コーチング稲垣友仁です。
今日のメルマガは先週土曜日に行なった講演会のダイジェスト版をお送りします。
11月8日(土)は、三重県教職員組合桑名員弁支部が主催する
「第44回桑名郡市子どもの未来を語る会」に講師としてお招きいただきました。
第44回ということで、もしかすると44年も続いている会なのかもしれません。
私がまだ教師だったころからこの会はあり、
当時は「母と女教師が語る会」という名前だったと思います。
母親と女性教師が交流しながら、子どもの育ちについて語り合う場として始まり、
そこから時代の流れとともに「子どもの未来を語る会」と名前を変え、
より幅広い人たちが集う会になっていったそうです。
■今回のテーマ
「子どもの才能を育むコーチングコミュニケーション 〜人と人との関わりの中で育む未来への力〜」
というテーマに、会場には100名を超える方々が集まり、講演とワーク、分散会を通して、
「子どもが自分から動き出す関わり方」について体験的に学びました。
■講演内容
今回お伝えした中心テーマは、「自律」と「心理的安全」。
いろいろな教育の論文を見ていくと、『子どもの学習意欲を長期的に高めるのは「自律」と
「安心感」がキーワード』 という研究結果が増えてきています。
特に今回は、デシとライアンの自己決定理論(*1)をベースに、
子どもが「自分で決める力」を育むために、
大人がどんな関わりをすればいいのかをお話ししました。
自己決定理論とは
人間がなぜ行動を起こし、
そのモチベーションをどのように持続させるのかについて言及された理論です。
人間には生来、
・「自律性」自分の行動を自ら決定したい
・「有能感」自分の能力を発揮し、効果的に活かしたい
・「関係性」他者と良好な関係を持ち、つながりを感じたい
という3つの心理的欲求があると言っています。
これらを満たされるとモチベーションがあがり、積極的に行動することになります。
特に、自律性が最も重要視され、「行動を自ら決定した」と感じることで
心理的な満足感が高まります。これは内発的動機づけといって、
自分の中から出てくるやる気が高まるのです。
教育・人材育成・マネジメント分野でうまく成果を出している人は、
上記の3つを押さえた関わりを行っているように思います。
コーチングコミュニケーションは、人と人との関わりの中で、
相手の意思を聞いたり、引き出したりなどの自律性を引き出し日々の行動に導いていきます。
特に相手の才能などを考慮した行動を引き出していくので、
自己決定理論の3つの心理的欲求を満たすには
うってつけの関わりになると思います。
その他の主な講演内容のダイジェストは下記です。
①相手の自律を導く
シーソーの法則:子どもとの関係において、大人が頑張りすぎると、
子どもは自律ではなく依存に傾きやすい。
→ 不安や責任を子どもに返すなど「任せる」「問いかける」「選ばせる」
関わり(コーチングコミュニケーション)へ。
子どもが自律的に体験することで学び成長をしていく。その支援をする。
②心理的安全性が学習を誘発する
心理的安全性とは、間違ったことを言ったとしても拒否されない雰囲気。
自分はこの場で認められているという肌感覚。
心理的安全性があると感じると脳の前頭葉がよりよく動き学習を促進。
心理的安全性を子どもが感じるには
・傾聴:評価せずに“今ここ”の感情を一緒に味わう。
受容と共感をベースに聞くことで自分を肯定できるようになる。
・承認:結果だけにフォーカスせずプロセスに対しても承認を。
「存在承認」と「行為承認」を日常的に言葉で伝えていくことで、
トライしてもいいと思える雰囲気が出来上がる。
③才能を伸ばす
リフレーミング:短所を強みに変える言葉の視点転換。
普段から子どもは才能を発揮している。
親が恐る子どもの行動には才能が隠れている可能性もある。
上記のポイントをついたコーチング的関わりが、
子どもに「安心して挑戦できる場、才能を発揮できる場」を生み出します。
一瞬では変わらないかもしれませんが、
長期的に見ていくと成長する環境に身をおくことになり、
子どものタイミングで変化する瞬間が訪れる可能性が高まります。
そこで何かをつかむと欲がでて自律スイッチが入りどんどんトライし始め、
そこで学習が起こり成長していくというイメージです。
■講演会で印象に残ったこと
特に印象的だったのは、講演会場にいた受講者の方で、
若い(30代前後)男性教師たちの積極的な姿でした。
私の問いかけに、自ら挙手し、発言してくれる先生方が何人もいました。
理由を聞くと、
「子どもに手をあげようと言っている以上、
自分もこういう場ではトライしなければと思いました」
その姿勢に触発されてか、どんどん自ら手を上げる方がでて、
場の空気がどんどん前向きに変わっていくのを感じました。
まさに、“関わりの中で未来が育まれる瞬間”でした。
■最後に
講演後のグループディスカッションでは、
「家庭ではティーチングが多くなっている」「子どもにどう寄り添うか」など、
現場のリアルな声が多く交わされました。
コーチングは“万能の魔法”ではありませんが、
「子どもとどう関わるか」を見直す視点を持つことで、
家庭も学校も職場も、もっと温かい学びの場に変わっていけると感じます。
あなたは最近、
「子ども(部下・仲間)の自律性を信じて任せた瞬間」はどれぐらいありましたか?
共創コーチング 稲垣友仁
参考文献:
*1:ロチェスター大学のエドワード・L・デシ(Edward L. Deci)教授とリチャード・M・ライアン(Richard M. Ryan)教授が提唱した「自己決定理論」(Self-Determination Theory:SDT)
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. Guilford publications.[https://doi.org/10.1521/978.14625/28806]
————-
※上記のコラムは、当社発行メルマガに掲載されたバックナンバーです。
下記のバナーから登録いただけば、毎週月曜日朝8時に、このようなコラムが届きます。
意識をもって一週間を始めることができます。